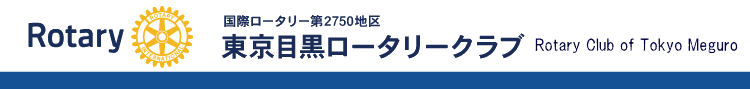チャーターメンバー 眞野 博会員
なぞかけ問答「ロータリーとかけて覚醒剤と解く、その心は、どちらもやめようとしてもやめられない」
チャーターメンバーの小川さんは一度やめても又戻ってきて神奈川県湯河原へ引っ越しても例会に出席し続けた。
広島原爆被害者の片岡修さん。愛知芸術大学の教授として招かれ名古屋へ行く時「又東京へ帰ってきたら目黒ロータリーへ来ます。よろしく。」と云って去っていったが、原爆後遺症で65才で亡くなられた。
清家清さんは足が弱かったので木村技研㈱の社長が長い間車で雅叙園まで送迎。「大丈夫ですか?」と尋ねるとステップをふんで健脚振りを示されたが、やがて姿が見えなくなった。「父の建築事務所までは私が車で送迎するんですけどロータリー迄は一寸・・・。父はしきりに出席したいと申すのですが・・」と娘さんとの電話での会話。
同じ顔触れの仲間と毎週顔を合せ、同じ会場で食事をするということは親兄弟以上の親密感が湧く。というよりロータリーは生活の一部になっていたからに外ならない。
日本のロータリークラブの誕生は大正9年米山梅吉さん等による東京ロータリークラブ。その時の会員選考基準は「国家的指導者であることを基準に選ぶこと。」日本銀行理事、正金銀行副頭取、興業銀行副総裁、日興証券社長、日本製鋼社長、富士紡社長、日本郵船副社長等々26名。昭和2年にはロータリーの拡大に伴って「会員選考を一層厳格にすることを決議」外国では考えられない会員を有した東京ロータリークラブがエリートクラブとして驚きの目で見られたのもうなずける。拡大に伴い、地域の指導者であること、或は専門職であることが基準とされ、職業分類が出来ると一業種1名の入会というように変わっていった。
1983年~1984年 東京目黒ロータリークラブの活動計画書。今から27年前、清家清さんが理事会決議でガバナーになった時の「奉仕の理想と題する」メッセージ掲載されている。「ロータリーが他の類似団体と異なっていることは職業分類に基づく会員制度から生まれているということです。みんなにロータリーを・・・というのは、あなたが代表する職業の中にロータリーの奉仕の理想を持ち込むことではないかと思います」と短く解り易い文章で結んでいる。
今は世界の為に、社会の為に・・とロータリーの理想、目的、行動もどんどん拡がっていって、長期計画書を読むとその主体が何なのか解らない有様。目黒ロータリークラブは学者、いわゆる大学教授の多かったのも特徴であった。初代会長鈴木桃太郎博士は爆発に関する日本の権威。これからの自衛隊の幹部は化学的知識がなければ時代の勝ち組みにはなれないと、化学を必修課目に取り入れた防衛大学を昭和28年に立ち上げた。教育にも通じた希有な化学者であった。そのような関係から博士号を持つ学者が多数目黒ロータリーの会員として集った。
横浜国立大学名誉教授だった北川徹三博士は昭和20年8月6日広島、8月9日長崎へ投下された原子爆弾の調査に、当時海軍技術中佐としていち早く出向き、その為のち、原爆後遺症で亡くなった。専門は炭鉱の粉麈、ガス爆発の検知、のち平和になってからは、酔っ払い運転のアルコール探知検査機の発明者として知られる。北川博士は国立横浜大学の学生が学ぶ「基本安全工学」という教科書の中で「東京目黒ロータリークラブの会員として志田正二会員(注)と共に社会奉仕委員を担当した時≪安全な生活≫と題する小冊子を作成して会員や関係者に配布したことがある・・。」となんと8頁に亙って記述し、横浜国立大学の学生に、教授という専門職を通じて奉仕の理想を持込みロータリーをPRしたのだった。
近頃は会員の間で「職業奉仕」「奉仕の理想」という、私共が教育され、体験したロータリーの原点に還ろうという気運が高まっている。米山梅吉さんではないが、日本には日本のロータリークラブの考え方があっても良いのではないかという訳である。
それにつけても会員にインタビューして思うことは東京目黒ロータリークラブには地域、職業の指導者等優秀な会員がよくもこれまで集ったということである。
注:志田正二理学博士 東京工業大学名誉教授 専攻 光化学 放射線化学
日本唯一の「化学辞典」の編集代表者
戻る
|